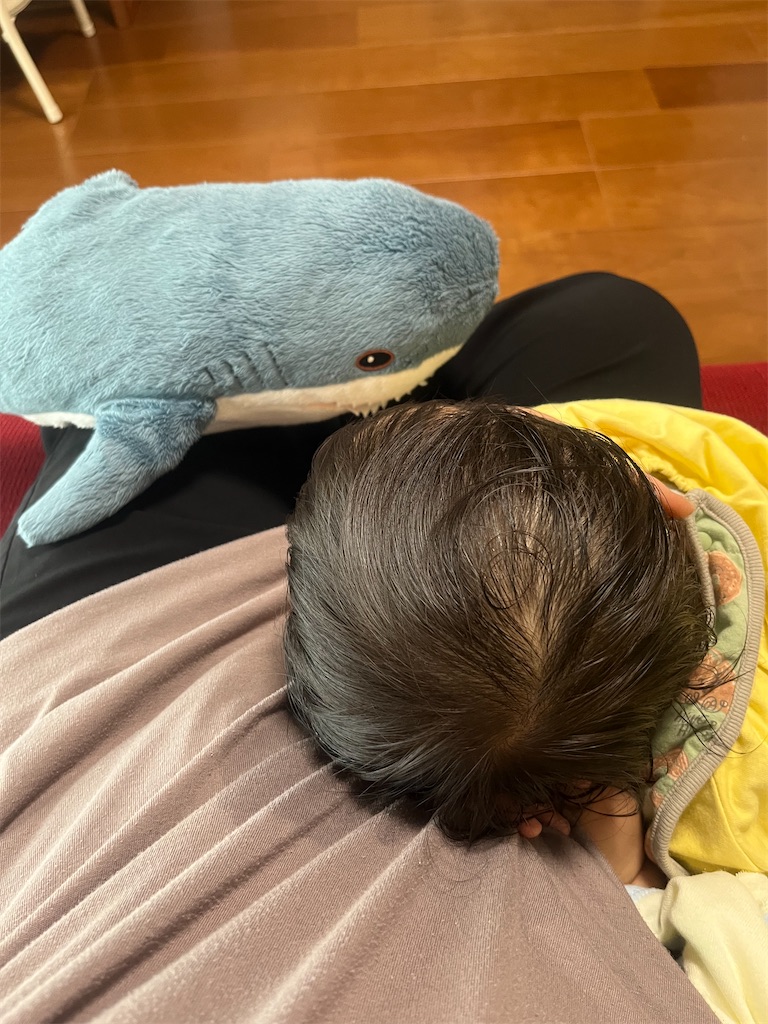おつかれサマンサタバサです。
そういえば職務経歴をブログには書いていなかったので
公開できる範囲で書いていきます。ぼかしてるところは、相手によりますが基本聞かれれば答えます。
現状転職志望は全然ないのですが、転職したくなった時にサッと出せる様に作りました。
カジュアル面談は子供寝たあとならいける。雑談に飢えているのでウェルカメ。
経歴
1991年生まれの富山出身です。32歳です。
小さいころから絵を描くのが好きでした。小学校の時、父親からPC-98Neを与えられたのがきっかけでタイピングができるようになり、パソコンが好きになりました。
学生時代
ニコニコ動画が見られるPC欲しさに地元の高専の情報工学科に入学しました。
成績は、めちゃくちゃいいでもないけど単位は基本落としていないはずです。
2012年3月に卒業しました。
1社目(地元SIer)
地元のIT企業に入社しました。当時はプログラマ志望でしたが(というかIT企業=プログラマだと思っていた)なんの因果かISP事業をやっている部署に配属になりました。そこからインフラエンジニアとしてのキャリアが始まっています。
Linuxの中でもDebian/GNU Linuが中心で、たまにRHELやCentOSがある感じです。Windows Serverも構築経験あるけど2回ぐらいしかありません。
深夜作業要員から数人規模のPMまでやっていました。
経験あるやつだけざっと書いていきます。
Postfix/Dovecot/Apache http Server/freeradius(あんまり自信ない)/ESXi/FortiMail/Squid/Zabbix
上の製品を扱う、ユーザー3万人規模のISP事業で使用するサーバの運用保守をしていました。退職する年は異動してOracleやintra martのサーバ構築とかもやってました。
著書「インフラ女子の日常」はこの時代から描き始めています。
新卒から9年勤めました。
2社目(現職・クリエーションライン)
1社目はオンプレミスやVM中心でしたが、コンテナやメガクラウドといったクラウドネイティブなインフラに興味が出てきたのと、ありがたいことにCTOからお声がけがあり転職しました。
入社してからはGoogle Cloudのお客様環境の保守とMongoDBのテクニカルサポートをやっています。今はほぼ後者です。
プライベート状況
夫と令和3年生まれ息子の三人家族です。将来的にもう一人欲しい。
できること・今後やっていきたいこと
インフラ構築や運用設計全般が好きです。落ちない仕組みとか知ると楽しくなります。
現在進行形でもしているけど、メガクラウドやコンテナ系といったクラウドネイティブな環境を経験してみたいです。
バックアップ/リストア設計、監視設計は割と嬉々としてやるし言われなくても色々試してみたくなるタイプです。ちょうど今はおうちのESXiでPrometheusで遊んだりしています。
ドキュメントを書くのに抵抗はないです。むしろ勝手に書きます。
執筆を経験して文章も書く体力もついたので会社のTech Blog書くのも割と好きです。検証しまくるから公開まで時間はかかるけど。
プログラミングはマジでさっぱりなので、スクリプトを書くとき毎度変数宣言から調べています。w
個人事業として「インフラ女子の日常」の続編も書いていきたいです。
今はテクニカルサポートの活用方法をわかりやすく伝える漫画を描きたいと思っています。
個人事業でイラストや漫画も経験あります。今の会社でも色々描いてます。
所有資格
IPA系:AD/FE/AP/SC
Google ACE(2021年取得)
蛇足情報:もう手放しましたがセロー250乗ってました。今はRX-8乗っています。
漢検2級/英検準2級/TOEICは聞かないでくれ(現在死にそうになりながら仕事で英文を書いています)
希望待遇
現職とほぼ同じなのですが・・・
・フルリモート勤務(地方勤務なのでどうしてもここがマストになっちゃいます)
・副業OK
・時短(少なくとも子供就学まで。現在は10:00-17:00)
・現職と同等かそれ以上の年収(聞かれれば答えます)
その他
登壇・執筆やインタビューしていただいた記事や登壇、執筆経験など
翔泳社さんのイベントはちょくちょく登壇の機会をいただいていてほんまありがたいかぎり・・・!
漫画描かせていただいたやつです。
自著です。
気になる人は一緒にスプラトゥーンしましょう。シーズン変わってA帯になったバレルスピナー使いです。
フレコ:8147-6116-6127